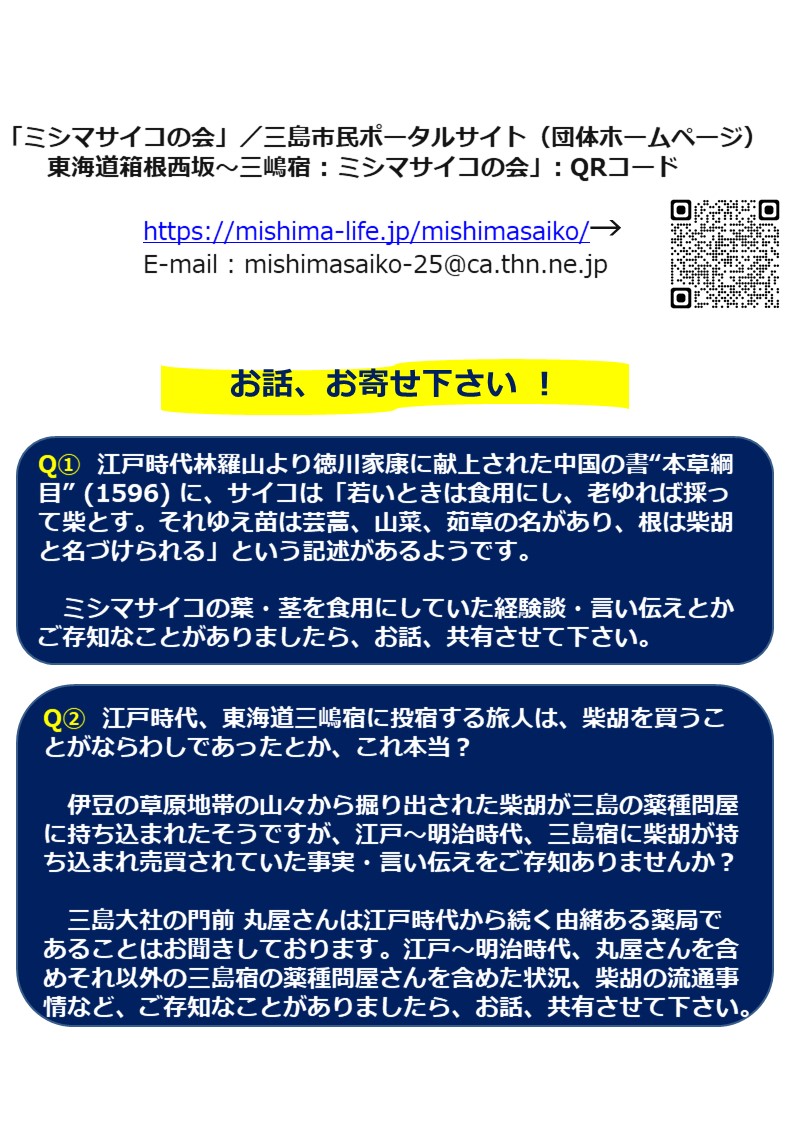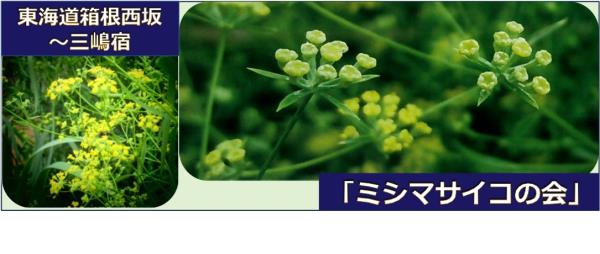

乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿(搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻)偼丄愝棫5廃擭偑宱夁偟儂乕儉儁乕僕傪奐愝偟傑偟偨乮椷榓尦擭7寧31擔乯丅
搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿儂乕儉儁乕僕偱偼丄僩僢僾儁乕僕偵壛偊丄乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿夛堳徯夘丒妶摦徯夘乮奐嵜僀儀儞僩丄乭摛廈儈僔儅僒僀僐庬傑偒懱尡夛乭偺椫乯丄乽儈僔儅僒僀僐乿忣曬丒嵧攟忣曬丄僒僀僐乛幠層丄儈僔儅僒僀僐偺岠擻丄奜晹儕儞僋儁乕僕側偳偑偁傝傑偡丅乽儈僔儅僒僀僐乿傪僉乕儚乕僪偵杮僒僀僩偵奆偝傑偺偍帩偪偺楌巎揑丄傑偨偼丄壢妛揑側忣曬彅乆傪偍婑偣捀偒杮僒僀僩偵宖嵹偝偣偰捀偗傑偡偲丄戝曄偁傝偑偨偄偱偡丅
栜榑丄忣曬採嫙埲奜丄偛堄尒丒偛姶憐傕戝娊寎偱偡丅
搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿偵嫽枴偺偁傞曽偼丄偳側偨偱傕夛堳搊榐偟儈僔儅僒僀僐傪惙傝忋偘傞妶摦傪巒傔傞偙偲偑偱偒傑偡偺偱丄偄偮偱傕偛楢棈偍懸偪偟偰偍傝傑偡丅
佀乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿 mishimasaiko-25@ca.thn.ne.jp
墈棗丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅
搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻 乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿偱偼丄乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿夛堳徯夘偵偰婰嵹偺傛偆偵2002擭傛傝 乭摛廈儈僔儅僒僀僐攄庬懱尡乭 傪奐嵜偟偰嶲傝傑偟偨丅攄庬夛偵偰20擭棃巊梡偝傟偰偄傞 乭摛廈儈僔儅僒僀僐乭 偺屆嫿偼丄乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿夛堳徯夘亂I亃傗乽儈僔儅僒僀僐乿忣曬亂I亃偵婰嵹偺傛偆偵摛廈撿埳摛挰偱偡丅
愭斒丄戞1夞偺攄庬懱尡夛傪奐嵜偝傟偨戝徖嬩晇巵偵偍榖傪偍巉偄偡傞婡夛偑偁傝傑偟偨(2025/6/29)丅挿擭丄儈僔儅僒僀僐傪垽偱偰偙傜傟偨戝徖巵偼丄杮棃丄儈僔儅僒僀僐偑帺惗偟偰偄偨撿埳摛丒壓揷乣徖捗傾儖僾僗丒搶埳摛乣敓撿丒廫崙摶丒擬奀敔崻摶丒敔崻惣榌乣晉巑嶳榌丒悶栰丒屼揳応側偳偺栰嶳偵儈僔儅僒僀僐偑嵞傃崻晅偒丄帺慠偲嫟惗偟偰偄偭偰傎偟偄偲偄偆丄寛偟偰椻傔傞偙偲偺側偄擬偄憐偄傪嫻偵摂偟懕偗偰偍傜傟傑偟偨丅嶐崱偺壏抔壔傗堎忢婥徾丄偝傜偵梲摉偨傝偺椙偄媢椝抧偺搚抧棙梡傗棦嶳惍旛偺偁傝曽偺曄梕偵傛傝丄娐嫬忦審偑戝偒偔曄傢偭偰偒偰偄傑偡丅敪夎偐傜弶婜惗堢傑偱偺惉挿偑娚傗偐側儈僔儅僒僀僐偵偲偭偰偼丄偦偆偟偨拞偱偺帺慠偲偺嫟惗偼偄偭偦偆擄偟偔側偭偰偄傞偺偐偲巚傢傟傑偡丅
偙傟偵懳偟偰丄攄庬夛乛庬傑偒懱尡夛丒儈僔儅僒僀僐僼僃傾側偳傪捠偠偰 乭摛廈儈僔儅僒僀僐乭偺僞僱採嫙偼23擭偑宱夁偟傑偟偨丅嬤椬偵偍廧偄偺嶰搰巗柉偺奆偝傑傪偼偠傔丄惷壀導撪奜傛傝偛嫽枴傪婑偣偰偔偩偝偭偨懡偔偺曽乆偵 乭摛廈儈僔儅僒僀僐乭 偺僞僱傪庤偵庢偭偰捀偄偨偙偲偲懚偠傑偡丅搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻敪 乭摛廈儈僔儅僒僀僐乭丄傑偩傑偩栰惈偺婥攝傪巆偟偨丄偳偙偐婥傑偖傟側栻憪偱偁傝傑偡偑丄奆偝傑偺恎嬤側娐嫬偺拞偱丄尦婥偵崻晅偄偰偔傟偰偄傟偽岾偄偱偡丅
亂偍抦傜偣丂2026/1/11 峏怴!!亃
乽儈僔儅僒僀僐乿島墘夛
丒擔帪丗椷榓俉擭俀寧俉擔乮擔乯丂侾係帪乣侾俆帪俁侽暘
丒応強丗嶰搰巗柉妶摦僙儞僞乕丂係奒夛媍幒
丒墘戣丗條乆側幘姵偐傜巹偨偪傪傑傕偭偰偒偨嫿搚偺栻憪乕儈僔儅僒僀僐傪尰戙偵惗偐偡乕
丒島巘丗栻嵻巘 楅栘彑梇巵乮儈僔儅僒僀僐偺夛夛堳丄偲偒偠偔嬩妝晹乯
乽儈僔儅僒僀僐僼僃傾乿
丒擔帪丗椷榓俉擭俀寧俀俀擔乮擔乯丂侾侽帪乣侾俆帪
丒応強丗妝庻墍揥帵応

乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿
丂杮夛偼丄2014擭2寧23擔丄10夞埲忋夞悢傪廳偹偰偒偨嶰搰帺慠傪庣傞夛庡嵜偺乽儈僔儅僒僀僐妛廗夛乿偵偰丄嶰搰偱愨柵忬嫷偵偁傞壜楓側墿怓偺壴偑嶇偔栻憪儈僔儅僒僀僐偺暅嫽傪栚巜偟17柤偱妶摦傪僗僞乕僩偟傑偟偨丅
丂儈僔儅僒僀僐偼丄偦偺崻偑娍曽栻偵梡偄傜傟傞惗栻丗僒僀僐(幠層)偺婎尨怉暔偱偡丅幠層偼丄拞崙嵟屆偺栻暔彂亀恄擾杮憪宱亁乮1乣2悽婭崰偺曇嶽丠乯偺忋昳乮挿婜暈梡偑壜擻側梴柦栻乯偲偟偰丄傑偨丄擔杮尰懚嵟屆偺栻暔帿揟杮憪榓柤乮918擭偵曇嶽乯偵傕廂嵹偝傟傞揱摑偁傞惗栻偱偡丅
嶰搰偼丄峕屗帪戙丄媽搶奀摴偺敔崻惣嶁偺廻応挰偲偟偰塰偊丄敔崻嶳榌乣晉巑嶳榌乣揤忛嶳榌乛埳摛敿搰偱帺惗丒嵦廤偝傟嶰搱廻偵廤壸偝傟偰偄偨幠層偺昡壙偑崅偔丄栻憪柤偲偟偰儈僔儅僒僀僐偲屇偽傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偐偮偰偼娭搶埲惣丄巐崙丄嬨廈側偳偺嶳栰偵帺惗偟偰偄傑偟偨偑丄棎妉偝傟丄崱傗娐嫬徣儗僢僪儕僗僩2017偱偼愨柵婋湝庬嘦椶 (VU) 偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅
丂巹払偼偙偺傛偆側尰忬偵娪傒乽嶰搰幠層乮儈僔儅僒僀僐乯乿傪傕偭偲巗柉偵廃抦偟丄娐嫬曐慡偲偲傕偵堦姅偱傕懡偔偺儈僔儅僒僀僐偑奨暲傒傪忺傞偙偲偑偱偒傟偽偲婅偭偰偄傞師戞偱偡丅
亂妶摦撪梕亃仢 庬帾偒懱尡丒島廗夛
仢 抧堟楢実妶摦偺懀恑
仢 島墘夛丒曌嫮夛偺奐嵜
仢 儈僔儅僒僀僐抦幆偺怺峩丒忣曬廂廤
仢 夛堳忣曬岎姺夛
丂丂丂丂丂丂丂丂丂側偳
乻夛堳曞廤丒偍栤偄崌傢偣愭乼
丂搶奀摴敔崻惣嶁乣嶰搱廻乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿偵嫽枴偺偁傞曽偵偼夛堳偲側偭偰丄堦弿偵偙偺抧堟丒妶摦傪惙傝忋偘偰偄偨偩偒偨偄偲巚偭偰偍傝傑偡両
偳偆偧奆偝傑偺偛巟墖丒偛嫤椡丄傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仚惓夛堳丗擭夛旓 2022擭搙傛傝柍椏
丂奆偝傑丄堦姅偱傕懡偔偺儈僔儅僒僀僐偺庬帾偒傪峴偄丄乽壞偺摛廈偺晽暔帊乿壜楓側墿怓偺儈僔儅僒僀僐偺壴傪堢傫偱偄偒傑偣傫偐丠
佀乽儈僔儅僒僀僐偺夛乿 mishimasaiko-25@ca.thn.ne.jp
佀 夛挿丗惎栰寶巌 kenji-hoshino@ny.thn.ne.jp丂